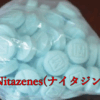アフリカ各地で広がる「反中国」暴動~中国の汚いビジネス
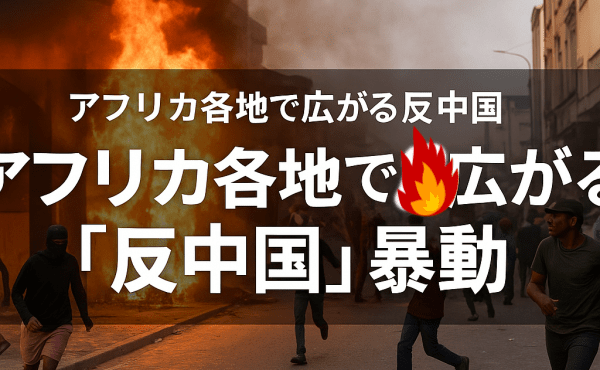
近月、アフリカ各地で中国企業に対する反発が強まっています。現地メディアによれば、労働環境や経済利益の不公平さへの不満から、企業周辺で抗議活動が発生し、店舗や倉庫の破壊、鉱山施設への襲撃にまで発展しました。
政府や国際機関が対話を呼びかけていますが、**「搾取に対する戦い」**として多くのアフリカ人に受け止められています。
マリのケース:金とリチウムをめぐる衝突
-
マリはアフリカで3番目に大きな金の埋蔵量を持つ国で、金が国家収入の25%以上を占める。
-
中国は2019年の一帯一路参加以降、60億ドル超を投資し、金生産の半分以上を掌握。リチウム鉱山も買収。
-
しかし現地住民は依然として貧困に苦しみ、環境汚染や劣悪な労働条件に不満を抱く。
2025年5月〜8月の事件
-
中国企業の鉱山・建設現場が武装勢力に襲撃され、中国人労働者が誘拐、身代金要求。
-
企業はやむなく作業停止・自爆的な資産破壊を行い、機材を埋めたりデータを破壊して撤退。損害は1億ドル超。
-
中国大使館は「即時撤退」を命令し、数百kmの危険なルートを避難行軍。
マリの鉱山は、もはや単なる産業拠点ではなく「戦場」と化しました。
アンゴラから広がる「反中」暴動
-
2025年夏、アンゴラの工業地帯で中国系工場への襲撃が発生。労働争議がきっかけで、群衆が工場や倉庫を焼き討ち。
-
ルアンダ市内は翌日には「戦場」のようになり、焼け跡や略奪品であふれた。
この動きはタンザニア、ケニア、南アフリカへ波及。
-
ケニア:モンバサの中国建設工業団地が封鎖・放火。ナイロビ中心部の中国系店舗も略奪。
-
タンザニア:ダルエスサラーム港の中国系施設が襲撃され封鎖。
-
南アフリカ:労働組合が大規模デモを組織し、物流拠点が襲撃。
中国の対応
-
中国外務省は「アフリカは高リスク地域」と警告。
-
緊急チャーター便や海軍艦船で自国民を避難。
-
国営メディアは「外国人嫌悪の犠牲者」として報じたが、現地の不満の根本原因(労働環境・環境問題)には触れず。
アフリカ諸国政府の立場
-
表向きは「暴力を非難」。
-
しかし内心では中国に「労働問題・環境破壊を改善せよ」と圧力。
-
一方で中国からの融資・貿易に強く依存しているため、板挟みの状態。
結果と影響
-
アフリカでの「反中感情」は単発の暴動ではなく、大陸規模の蜂起の様相を呈している。
-
港湾封鎖による物流停滞、鉱山閉鎖による資源供給不安定化など、経済への打撃が拡大。
-
今後はエチオピア、ナイジェリア、ザンビアといった他の中国拠点にも飛び火する恐れ。
中国のアフリカ支配の手法
-
借金漬け戦略(債務外交)
巨額のインフラ投資を持ちかけ、返済困難に陥った国の港・鉱山・土地の権益を長期的に握る。 -
資源収奪型投資
金・石油・リチウムなどを大量に輸入。利益の大半は中国企業へ還流し、現地住民には雇用や利益がほとんど残らない。 -
労働者持ち込み
プロジェクトに中国人労働者を大量投入し、現地雇用や技術移転を制限。 -
政治的影響力の浸透
援助や賄賂を通じて政府要人を取り込み、国連など国際場裏で中国寄りの投票をさせる。 -
環境・労働軽視
過酷な労働条件や環境破壊を放置し、不満が現地社会に蓄積。
まとめ
-
アフリカ各地で中国資本への反発が暴力に発展。
-
マリでは鉱山が襲撃され、中国人労働者が誘拐、資産破壊。
-
アンゴラを震源に、タンザニア、ケニア、南ア、各国で中国企業が標的に。
-
中国は避難を急ぎ、アフリカ政府は板挟みに。
-
背景には「搾取への怒り」と「環境・労働問題」があり、単なる一過性ではなく構造的な対立が根底にある。
このような中国の他国支配のやり方が人道的にいつまでも許されるわけがありませんね。