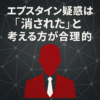移民は“ゼロ円で輸入できる資源” ― 先進国既得権益者の最強ビジネスモデル

「移民政策は失敗だ!」と先進国では常に批判が起きている。
治安の悪化、文化の破壊、福祉コストの増大…。
しかし、なぜ政治家や大企業はやめようとしないのか?
答えは簡単だ。移民は彼らにとって “ゼロ円で輸入できる資源” だからだ。
第1章 移民は“輸入コストゼロ”の資源
石油や鉄鉱石を輸入するなら、代金も輸送費も払わねばならない。
だが労働力という資源(=移民)は違う。
-
旅費や手数料は 本人や母国の仲介業者が負担。
-
受け入れ国は「入国させるだけ」で労働力を確保できる。
つまり、移民は “勝手に自分の足で歩いてやって来る資源” なのである。
第2章 コストは“社会化”される
移民を受け入れた後の医療・教育・住宅・福祉コストは、すべて 税金 でまかなわれる。
企業は安い労働力を使えるが、その維持費は国民に押し付けられる。
要するに、
-
仕入れコストはゼロ
-
維持コストは国民の血税
この仕組みは、まさに “無料で仕入れ、国民に代金を払わせる悪魔のビジネスモデル” である。
第2章補遺 ― 福祉コスト増大=税金公金中抜きチャンス拡大
移民受け入れで最も批判されるのが「福祉コストの増大」。
だがその裏では、これが 中抜きビジネスの拡張 になっている。
予算が膨らめば“口利きビジネス”が動く
-
国から自治体に一括交付された予算は、NPOや社団法人、コンサルに丸投げされる。
-
ここで「口利き」「談合」「水増し請求」が横行。
-
予算が大きいほど、中抜きの取り分も増える。
-
「多文化共生推進事業」や「外国人相談窓口」への交付金。
-
通訳・翻訳・生活支援など測定しづらいサービスが多く、水増しが容易。
-
さらに監理団体や登録支援機関は 月額管理費を外国人本人から徴収 → 事実上の二重取り。
つまり、福祉コスト増大は単なる「負担」ではなく、税金を利権に変える装置なのだ。
第3章 誰が儲かるのか ― 国別の事例
ドイツ ― 「受け入れ産業」が公費で潤う
2015年以降の難民大量流入で「統合失敗」と言われたドイツ。
だが裏では、連邦政府からの補助金(難民1人あたり月数十万円規模)が自治体に流れ、そこからNPO、語学学校、住居提供業者、弁護士に金が落ちる。
“難民ビジネス” と呼ばれる市場が形成され、関係業者は潤った。
イタリア ― NGOと港湾都市の利権
地中海を渡る移民船の収容は社会問題化している。
だが港湾都市では、施設運営や食事提供で 1人1日数十ユーロの公費契約 が成立。
運営団体や政治家まで資金が回り、「移民流入は止められない方が得」という構造ができあがった。
アメリカ ― 農業・建設・外食の低賃金依存
移民の急増で「不法移民」「賃金停滞」が批判されるアメリカ。
しかし裏では、農業・建設・外食の巨大ロビーが低賃金労働力を確保するために移民を後押し。
富裕層や企業オーナーは儲け、社会保障と地方財政の負担は庶民に転嫁されている。
日本 ― 「監理団体」「支援機関」の新しい飯のタネ
技能実習・特定技能制度の下で、監理団体や支援機関は 1人あたり月数万円の管理料 を徴収。
多文化共生の名の下に補助金・交付金も流れ込み、移民は “金になる商品” と化している。
第4章 政治家は馬鹿ではない ― 利権を最大化しているだけ
「ヨーロッパで失敗しているのに、なぜ日本は後追いするのか?政治家は馬鹿なのか?」
そんな議論をよく目にする。
だが違う。彼らは馬鹿ではない。
すべて分かったうえで、国の文化が破壊されても、治安が悪化しても、国民が貧しくなっても、自分たちが儲かれば構わないのだ。
そして最終的に日本が弱体化して住みにくい国になれば、
吸い上げた資産を持って海外に逃げるだけ。
庶民だけが取り残される。
結論
移民は “ゼロ円で輸入できる資源”。
だから政治屋と大企業にとって、これほど都合のいい政策は存在しない。
ヨーロッパの「失敗」から学ぶのではなく、
その裏で動く “移民ビジネスモデル=税金中抜きシステム” を真似しているに過ぎない。
彼らは馬鹿ではない。
ずる賢い卑怯者 なのだ。
庶民が声を上げない限り、
“タダで仕入れた資源”として移民が無限に投入され続ける。